導言
佛陀的教えは、3,000年を超える歴史を持つ世界三大宗教の一つです。紀元前6、5世紀に誕生した仏教は、インドのシャカ族のシッダールタ・ガウタマによって創始されました。伝法は、漢朝時代に中國に伝わります。
漢伝仏教
仏教は、漢朝以降、中國に浸透し始めます。最も古い文獻によれば、紀元前2年頃には仏教が伝わっていたようです。隋唐時代には仏教が隆盛し、天台宗、浄土宗、禪宗など、中國獨自の宗派が形成されました。これらは朝鮮半島、日本、ベトナムなどに伝えられました。中國仏教には、かつて數多くの流派がありましたが、現在主流となっているのは「八大宗派」です。すなわち、三論宗、瑜伽宗、天台宗、賢首宗、禪宗、浄土宗、律宗、密宗です。とりわけ禪宗と浄土宗は、中國に広く普及しています。
蔵伝仏教
7世紀のソンツェン・ガンポ王の時代に、仏教がインドと中國からチベットに伝わりました。チベット仏教は伝世の違いにより、ニンマ派、サキャ派、カギュ派、ゲルク派などの宗派に分れています。また、化身ラマによる継承制度が確立されました。その中のゲルク派は、15世紀にツォンカパによってカダン派を基盤に創始されました。その後、蔵伝仏教の諸宗派の中で最も影響力のある宗派となりました。ダライ・ラマとパンチェン・ラマという2つの化身ラマの體系は、いずれもこの宗派に屬します。
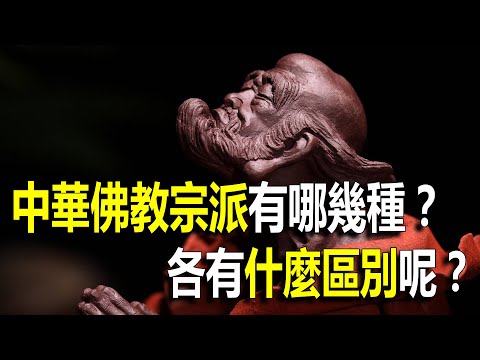

南伝上座部仏教
中國の雲南省西雙版納タイ族自治州、徳宏タイ族チンポー族自治州などに伝わる南伝上座部仏教は、7世紀頃にビルマから伝わりました。雲南の南伝仏教には、潤派、擺莊派、多列派、佐底派の4つの宗派があり、タイ族、プーラン族、阿昌族などの少數民族に伝えられています。中華人民共和國成立後、中國の仏教は民主改革を経て、社會主義社會に適合する道を歩みました。1953年5月30日、中國仏教協會が発足し、1956年に中國仏學院が、1987年には中國チベット語系高級仏學院が設立されました。各地にも分會や地方仏教協會、地方仏學院が相次いで設立されました。
仏教宗派
仏教は、思想や組織としてある程度の発展を遂げると、各宗派に分かれるという避けられない性質を持っています。2,000年を超える伝播と発展の中で、仏法の理解や解釈の違い、また環境の変化への対応による仏教思想の分化により、様々な宗派が誕生しました。
現代の仏教
現在の仏教には、上座部仏教、大乗仏教、密教という3つの主要な系統があります。この3つの系統の下にも、さらに多くの宗派に分かれています。これら3つの系統は、教義の理解や修行法の違いがあり、上座部仏教と大乗仏教、顕教と密教、難行道と易行道という分類にもつながっています。

學術研究と大眾の認識
學術研究や大眾の認識では、教義や修行法の相違によって分けられた宗派が、歴史や地理によって混同して示されることがあります。例えば、上座部仏教は南伝仏教とも呼ばれ、大乗仏教は北伝仏教や漢伝仏教とも呼ばれます。また、密教は金剛乗や蔵伝仏教とも呼ばれます。こうした混同により、概念上異なる宗派が同一視されてしまうことがあります。例えば、「南伝仏教」と「上座部仏教」は、実際には違いがありますが、「南伝仏教」や「上座部仏教」は、しばしば大乗信者から「小乗仏教」と軽んじられます。しかし、上座部仏教は、「大乗」や「小乗」という用語は仏陀が説かれたものではないと考えています。大乗の経典では、上座部仏教を聲聞乗のみがあると描寫しています。一方、上座部仏教の依拠するパーリ語経典には、聲聞菩提、闢支菩提、三藐三菩提(仏菩提)が含まれています。「大乗仏教」、「北伝仏教」、「漢伝仏教」も、しばしば同一視されています。「金剛乗」、「密乗」、「密宗」、「蔵伝仏教」も同様です。こうした混同は、不必要な宗派間の対立を深める一因となっています。現代の學術界では、仏教史の研究から、これらの概念を整理して區別しています。
仏教の分裂
社會政治、宗教競爭、その他の理由により、12世紀以降、仏教はインド本土から消滅しました。現在は地理的な區分から南伝と北伝に分けられていますが、一般的には南伝仏教、漢伝仏教、蔵伝仏教という分け方が用いられています。北伝仏教は、主に北方からシルクロード経由で中央アジア、中國、朝鮮半島、日本などへ伝わった仏教で、梵語や各種中央アジアの言語、中國語の経典を有しています。北伝仏教は現在、漢伝仏教と蔵伝仏教に分かれています。
部派仏教と大乗仏教
學術研究では、一般的にインド仏教が中心とされ、部派仏教、大乗仏教、秘密大乗仏教が仏教発展史の段階であるとされています。さらに、初期仏教というより古い段階まで遡ります。
部派仏教の分裂
仏陀の入滅後100年ほど経った頃、インドで最初の仏教の分裂が起こりました。比丘たちが戒律を厳格に遵守すべきかどうかをめぐって激しく議論しました。一方の派閥は戒律を無條件に遵守すべきと主張し、もう一方の派閥は戒律の実踐細節においては融通を利かせるべきだと主張しました。彼らは「十事非法」と呼ばれる10の事柄について議論しました。例えば、出家者は金銭の佈施を受け取ることができるか、托缽で得た塩を貯蔵することができるか、無脂乳を混ぜずに飲むことができるかなどの問題です。
上座部と大眾部
スリランカに伝わった赤銅鍱部によれば、仏教僧団は戒律を厳格に守る上座部と、戒律の実踐細節を融通することができる大眾部に分裂しました。しかし、大眾部が伝えた『摩訶僧祇律』には、十事に関する戒律も明記されており、この段階では仏教は分裂していなかったと考えられます。
根本分裂
本當の分裂は、『異部宗輪論』に記録されているとされています。仏陀の入滅後116年、比丘の大天がマガダ國で、阿羅漢の殘存意識や悟りの機縁に関する5つの問題を挙げて仏教の根本的な分裂を引き起こしました。その後、議論は「阿羅漢に後退があるかどうか」(6種の阿羅漢、9無學)などの問題にも及びました。
部派仏教の再分裂
第1回目の分裂後、ほどなくして上座部と大眾部がさらに多くの部派に分裂しました。
大乗仏教の誕生
大乗仏教の思想は、紀元1世紀頃に生まれます。部派仏教が後になると理論化や教條化が進みすぎたことに対し、大乗仏教は「仏陀の根本の精神を探求し、枝葉の末節を放棄する」という原則を打ち立てました。大乗仏教の思想家の中には、「部派仏教は保守的で分析的な學問的仏教であり、大乗仏教は開かれて原則的な実踐的仏教である」と考える者もいます。しかし、部派仏教の信徒たちは大乗仏教に異議を唱え、自身の伝統を守り続けました。
中観派
中観派は、紀元2世紀に龍樹によって創始されました。弟子である提婆が主な論師です。根本的な依拠文獻である『中論』に由來して名付けられました。
**中観派は、世界上の一切のものは相対的で依存関係にある(縁起、縁會)とします。それらは借り物の概念や名相(仮名)であり、それ自體としては不変の実體や自性(無自性)を持たないと説きます。中観派は、『般若経』の真諦と俗諦、中道第一義諦、『瓔珞経』の二諦義、すなわち八不中道などを依拠する理論を打ち立てました。
瑜伽派
瑜伽派は、紀元4世紀に無著によって創始されました。弟の世親が主な論師です。根本的な依拠文獻である『瑜伽師地論』に由來して名付けられました。
**瑜伽派は、すべてのものは、人々の精神の集合體である識が変現させたもので、『三界唯心』、『萬法唯識』と説きます。人は眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識、末那識、阿頼耶識の8つの識を有するとされています。その中の第8の識(阿頼耶識)は、すべての「種子」を保持し、因果の輪廻の主體とされます。瑜伽派はまた、「五位百法」の理論體系も打ち立てました。
唯識派と如來蔵派
唯識思想は南北朝時代に中國に伝わりました。唐の時代、玄奘がインドから帰國して『成唯識論』を翻訳すると、漢伝仏教はこの経典に基づいて唯識派を創始しました。
**如來蔵派は、人は本來的に清浄な自性、すなわち如來蔵を有すると考えています。堅慧、智光などの論師が代表的な人物です。唯識派と中観派はどちらもこの派の影響を受け、漢伝仏教の主流となっています。
密教の段階
密教発展の段階では、インドでは密教の経典の內容によって分類する方法と、密教の経典が完成する順序によって考える方法があります。『大日経』と『金剛頂経』が完成した時期をインドの「中期密教」または純密と見なし、それ以前は「初期密教」または雑密、それ以後は「後期密教」または無上瑜伽とします。
密教の理論
密教は理論的には、大乗仏教の3つの主要な學派とすべて関係があります。
仏教の中國伝來
仏教は漢の時代頃から、インドから西域を経由して中國に伝わりました。當初は主に仏典の輸入と翻訳が行われました。
漢伝仏教の隆盛
仏教は漢の時代から中國で徐々に広まって発展し、特に南北朝時代には多くの皇帝が仏教を崇拝し、膨大な仏典が翻訳され、仏教徒や仏教學者の數も急増しました。一方、仏教が伝來する過程で、儒教思想や道教思想などの影響を免れず、一部は中國の風土に合わせた形に変わりました。こうして漢地では獨自の仏教思想と理論が形成され、漢伝仏教の宗派が形成される土壌が整いました。
漢伝仏教の鼎盛期
隋唐時代は漢伝仏教の鼎盛期であり、主要な宗派がすべて成立し、発展はかなりの規模に達しました。しかし、仏教発展過程で生じた諸問題や、三武の法難による4度の法難により、多くの仏典が破壊され、多くの宗派が大きな打撃を受け、かつての輝きを取り戻すことができなくなりました。しかし、禪宗と浄土宗だけは文字を立てず、學問色が薄く、比較的自立した経済基盤を持っていたため、法難の後もむしろ繁栄し、今日に至っています。
中國仏教の宗派
中國仏教には、8つの大乗宗派と、「小乗宗派」と見なされる2つの宗派(成実宗と倶舎宗)があります。そのうち、大乗の8つの宗派が広く普及し、影響力が大きくなっています。今日、十三宗派説もあります。梁啓超の『中國仏法興衰沿革説略』では、大乗摂論宗、小乗倶舎宗、十地宗、三論宗、法華宗、涅槃宗、天台宗、法相宗(唯識宗、慈恩宗)、華厳宗、浄土宗、律宗、密宗、禪宗の宗派が挙げられています。季羨林は、律宗は宗派にはなりえず、浄土宗は獨自の固有の理論を持たず宗派ではないと主張しています。また、成実、倶舎は學派であって宗派ではなく、三論宗は後に天台宗、禪宗に吸収されて獨立した宗派として成り立ちえないと主張しています。宗派になることができたのは、天台宗、華厳宗、法相宗、禪宗の4つのみであるとしています。以下、それらをそれぞれ簡単に説明します。詳細はについては、それぞれの宗派の項目を參照してください。
天台宗
延伸閲讀…
佛教派別- 維基百科,自由的百科全書
大乘佛法八大宗派: 禪宗、淨土宗、密宗、律宗…等。
天台宗は中國で最初に創始された宗派であり、創始者の智顗が浙江省の天台山に居住していたことから得名しました。その教義は主に『妙法蓮華経』に基づいており、法華宗とも呼ばれています。
**天台宗の主要な思想は、実相と止観であり、実相を用いて理論を明示し、止観を用いて実踐を指導しています。提示する理論には、十如是、一念三千、一心三観などがあります。この宗派は、南北の各家の學問と禪観の説を集大成しており、理論體系が整っていて、後の宗派に大きな影響を與えています。天台宗は、中國文化がインドの仏教を受け入れ、中國の仏教界の知識人が獨立して思考し、新しい仏教理論體系を創造するという獨自の新仏教理論體系です。その革新的な実相論の立場は、隋唐以降、中國仏教の歴史の中で重要な理論上の議論の主題の一つとなっています。その禪観の修行法も、中國仏教界で代々受け継がれてきた重要な修行法の一つとなっています。その五時八教の判教理論は、それ以降、すべての仏教理論家の理解の輪郭として、仏教理論の研究の土台となっています。
5.念想3.行頭2.引用欄
佛教派別
佛教派別泛指佛教歷史悠久以來,因教義分歧、地域差異、時代變遷而形成的各種分支與流派。這些派別之間存在著不同的修持法門、教義觀點與組織形式。
| 佛教派別 | 起源 | 地區 | 主要教義 |
|---|---|---|---|
| 上座部佛教 | 公元前3世紀左右 | 斯里蘭卡、緬甸、泰國 | 以原始佛教經藏(南傳上座部三藏)為依據,強調個人實踐與戒律的嚴謹。 |
| 大乘佛教 | 公元1世紀左右 | 印度、中國、日本 | 在上座部佛教的基礎上發展,強調慈悲、智慧與空性,主張一切眾生皆有成佛的可能性。 |
| 密宗佛教 | 公元7世紀左右 | 西藏、蒙古、尼泊爾 | 結合了上座部、大乘教義與地方傳統,強調儀軌、持咒與冥想,重視師承傳授。 |
| 淨土宗 | 公元6世紀左右 | 中國、日本、韓國 | 主張唸佛往生西方極樂世界,強調禪定與淨化內心,往生後可以成佛。 |
| 禪宗 | 公元6世紀左右 | 中國、日本、韓國 | 強調心性本淨,見性成佛,不依賴經書教條,重視實證和直覺領悟。 |
| 華嚴宗 | 公元7世紀左右 | 中國、韓國、日本 | 以《華嚴經》為依據,主張一切眾生彼此相攝,圓融無礙,成佛是一切眾生的共同目標。 |
| 天台宗 | 公元6世紀左右 | 中國、日本、韓國 | 以《法華經》為依據,主張一切法門皆為成佛之道,強調止觀雙修與圓融中道。 |
| 律宗 | 公元7世紀左右 | 中國、韓國、日本 | 專門研究戒律學,強調持戒清淨,以戒為本,是維持僧團紀律的重要派別。 |
